クラウドファンディング導入イメージ
INTRODUCTION IMAGE

クラウドファンディングで達成したいこと
世界に誇る日本の鍛治技術を継承するために、認知向上と継承者へアピールしたい!
日本の鍛治技術を継承し、世界に広めるためのクラウドファンディングでは、「伝統と革新の融合」をテーマに認知向上と支援者獲得を目指すことが効果的です。技術継承と後継者育成や、日本鍛治技術の認知拡大などプロジェクトの目的を明確にすることで、多くの支援者を集めることが可能です。
ビジネス・起業のクラウドファンディング達成ポイント
1
プロジェクトの目的を明確化- 後継者不足に直面している鍛治業界で、技術を継承し、新たな職人を育てるための支援を募ること、そして、世界中の人々に日本の鍛治技術の素晴らしさを知ってもらうために、動画、展示会、オンラインコンテンツを制作するなど、プロジェクトの具体的な内容・目的を明確にします。
2
プロジェクトの背景と魅力を伝える-
日本の鍛治技術がいかに独特で歴史的価値があるかをわかりやすく伝える(刀鍛冶、包丁、工芸品など)ことで、歴史と文化の紹介を魅力的に表現します。
また、職人の高齢化、後継者不足、現代生活との接点の減少など、技術が消失するリスクを明示し、現在の課題も伝えます。そして、日本の鍛治技術は世界でも評価が高く、後世に伝えられることで新しい文化や産業を生み出せることを強調し、今後の可能性についても提示します。 3
魅力的なリターンの提案-
リターンは鍛治技術の価値を直接体験できるものや、支援者が技術の保護に貢献したと実感できる内容を設定します。
<製品型リターン>
・クラウドファンディング限定デザインの包丁、ナイフ、小物(アクセサリーや文房具)。
・支援者の名前を刻印した特注品。
・職人の手作業による美しい作品(装飾品やアート作品)。 など
<体験型リターン>
・鍛治体験ワークショップ
・鍛治工房ツアー
・職人との交流イベント など
<デジタル・教育型リターン>
・制作過程の映像や写真
・鍛治技術の歴史や基礎知識を学べる電子書籍 など
<感謝型リターン>
・名前入りの感謝状
・デジタル感謝カード など 4
認知向上のためのプロモーション-
<SNSや動画コンテンツを活用>
・鍛治の技術や工程を動画や写真で紹介(Instagram、YouTube)。
・SNSで「#日本鍛治の未来」「#伝統技術を守る」などのハッシュタグを使用し拡散。
・短い動画で「火花が散る鍛治の現場」や「刀のように輝く包丁」などを魅せる。
<職人を主役にしたストーリー作り>
・伝統を守り続ける職人の人生や哲学、仕事にかける思いを伝える。
・若手職人が挑戦する姿を記録し、未来への希望を示す。
<地域や国際イベントと連携>
・地域の祭りや展示会で鍛治製品をPRし、クラウドファンディングを告知。
・海外での日本文化イベントでプロジェクトを紹介し、国際的な支援を募る。
クラウドファンディングの流れ
-
STEP.01
企画構成・ストーリー作成
鍛治技術の歴史や伝統、地域の情報など、バックグラウンドをお聞きして企画構成、ストーリーを作成します。
-
STEP.02
リターンの設計・構築
支援してもらいやすいリターンを、プロジェクト起案者の想いを込めて設計します。
-
STEP.03
ライティング・プロジェクトページデザイン制作
構成、ストーリー、リターンのわかりやすさなどを考慮した、ライティング、デザインを行います。
-
STEP.04
SNSでの告知サポート
クラウドファンディング開始まで、告知のSNS配信を行います。
スタート日に合わせてカウントダウンをするなど、クラウドファンディングのスタートダッシュができるように盛り上げていきます。 -
STEP.05
スタートから終了まで見守りながら施策をします
目標達成した場合は、ネクストゴールの設定や告知をします。
もし反響が少なければ、SNSでの告知を増やしたり、活動報告の更新などをこまめに行い、随時ユーザーに訴える施策を行います。 -
STEP.06
終了後の対策もお任せください
クラウドファンディング終了後は、支援者へのお礼の掲示や、イベント開催、ニュースレターの配信などさまざまな試作が必要です。
ビジネス・起業のクラウドファンディングはぜひFUNDBOOSTへ!
上記の具体的なイアデアは、すべてFUNDBOOSTにて対応が可能です。
クラウドファンディングチャレンジについてもっと詳しくお知りになりたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。




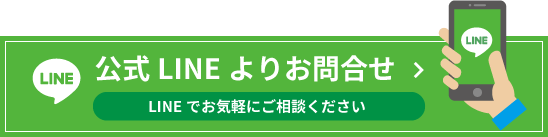
 LINEでお問い合わせ
LINEでお問い合わせ