復興支援でできることは?注意点やクラウドファンディングの事例も紹介
公開日:2024年11月03日
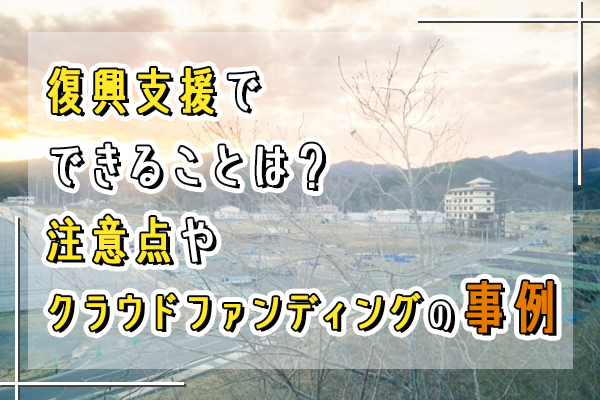
復興支援の形はさまざまで、思わぬ活動が支援につながることもあります。自分の状況や環境に応じて、復興支援としてできることを、無理のない範囲で取り組むことが大切です。今回は、復興支援でできることと注意点を解説します。
クラウドファンディングの復興支援プロジェクト事例も紹介するので、ご参考にしてみてください。
復興支援とは
復興支援とは、災害や事故などによって被災した地域や人々の生活を立て直すための活動のことです。具体的には、現地での炊き出しや被災家屋の片付けなどのボランティア活動、団体を通じたお金や食材などの寄付、復興支援商品の購入による応援などをおこないます。
復興支援の形は、直接的なものから間接的なものまでさまざまです。自分のできることから始めて、被災地の一日も早い復興を願うことが大切です。
復興支援でできること

個人が復興支援でできることには、募金、ボランティア活動、復興支援商品の購入などがあります。SNSなどでの情報拡散や、クラウドファンディングでの支援も、復興支援に含まれます。復興支援でできることを詳しく紹介します。
自治体や支援団体への募金
自治体や支援団体へ、直接募金する方法です。募金活動は街中でおこなわれているため、外出時に気軽に支援ができます。募金をするときは、募金を募っている支援団体が信頼できるか、慎重に判断しましょう。
ボランティアとして現地に赴く

ボランティアとして現地に赴き、炊き出しや被災家屋の片付けなどをする方法もあります。被災者の方々と直接会って、物理的な支援ができるため、復興支援として大きな力となるでしょう。
しかし、一方で現地でのボランティア活動は、無計画におこなうと却って迷惑をかけてしまう可能性があります。ボランティアとして現地に赴く場合は、事前にしっかりと準備をおこない、現地では現場の人の指示に従ってマナーを守り活動するようにしましょう。
復興支援商品を購入する
復興支援商品とは、自然災害などで被災した地域で作られた商品のことです。復興支援商品を購入すれば、被災地の事業者に収入が入ったり、売上の一部を支援金に充ててもらったりすることができます。被災地の雇用創出や地域経済の活性化にもつながります。
SNSなどで情報を拡散する
![]()
SNSなどでの被災地情報の拡散も、復興支援のひとつです。被災地の最新状況を拡散することで、支援者を増やすことができます。ボランティア募集や復興支援商品紹介など、SNSを通じて情報を拡散すれば、多くの人の関心を集められるでしょう。
クラウドファンディングで支援する
クラウドファンディングでは、復興支援プロジェクトがたくさんあります。スマホから気軽に支援ができるため、個人ができる復興支援の方法としては、最も気軽で取り組みやすいといえるかもしれません。
支援するプロジェクトを自分で吟味して、団体の信頼性などもインターネットで調査し確認できるため、安心して支援しやすいのもクラウドファンディングで復興支援をするメリットです。クラウドファンディングでは500円ほどからの小額支援から、数万円以上の高額支援まで、無理のない範囲での支援ができます。
復興支援をするときの注意点
復興支援をするときの注意点は、被災地の最新状況を把握することです。被災地の状況は、日々変化しています。適切なタイミングで適切な支援が出来るように、最新状況を確認し、被災地が求めているものを提供できるよう努めましょう。
募金をしたり復興支援商品を購入したりするときは、信頼できる団体であるか確認することも大切です。団体の過去の実績や寄付金の使い道などが明確であるか、 詐欺の可能性も視野に入れて、慎重に判断しましょう。
ボランティア活動として現地に赴く際は、却って被災地の復興活動の妨げとならないよう、事前に現地に赴いてもいいか確認することも重要です。
クラウドファンディングの復興支援プロジェクト事例
クラウドファンディングは、個人が支援しやすい復興支援の形のひとつです。自分で支援したいプロジェクトを選べて、支援金額も調整できるため、 無理のない範囲で応援したい復興支援活動のサポートができます。クラウドファンディングの復興支援プロジェクト事例を紹介します。
能登半島地震から未来に向けた力強い一歩を。復興に向けた活動を強力に推し進めたい!
能登半島地震の復興支援プロジェクトです。能登が能登らしく復興するために支援者を募り、集まった資金は自主避難所の開設と運営、⺠間物資支援受け入れ協力、炊きたてご飯の提供支援など、さまざまな復興支援に役立てられました。最低支援金額は3,000円で、お礼のメッセージや活動報告などがリターンとなっていました。
参照:https://camp-fire.jp/projects/736115/view?list=projects_tag_restoration_most_funded
【小倉昭和館再建】~まちの小さな映画館、奇跡の復活を夢見て~
創業83年の記念日を前に襲った火災で焼失した、福岡の単館系上映館・小倉昭和館の再建支援プロジェクトです。プロジェクトは成功し目標金額を達成、再建が決定しました。
最低支援金額は3,000円で、お礼のメッセージや活動報告、オリジナルグッズなどがリターンとなっていました。
参照:https://camp-fire.jp/projects/647139/view?list=projects_tag_restoration_most_funded
炉端焼き発祥の店!もらい火で全壊。おばあちゃんの店を救ってください!
北海道で70年の歴史がある炉端焼き発祥店『炉ばた』がもらい火で全壊してしまったことによる、お店の再建支援プロジェクトです。
炉ばたの名物おばあちゃんが守ってきた店を復活させるために、多くの支援者からの支援がありました。プロジェクトは成功し目標金額を達成、再建が決定しました。
最低支援金額は3,000円で、心の込もった感謝のメールや活動報告、お店のロゴ入りグッズなどがリターンとなっていました。
参照:https://camp-fire.jp/projects/622569/view?list=projects_tag_restoration_most_funded
クラウドファンディングで復興支援をするメリットとデメリット
クラウドファンディングで復興支援をするメリットは、小額からの支援ができ、透明性が高いことです。クラウドファンディングではプロジェクトにもよりますが、500円ほどからの少額支援ができます。
クラウドファンディングのプロジェクトは審査を通過したものだけが公開されるため、起案者の信頼性が高く、寄付金の使い道も細かく明示されるなど、透明性が高いこともメリットです。
従来の募金方法と比較すると、迅速な資金調達が可能であることから、被災直後の緊急的な支援役立つメリットもあります。プロジェクトによってはリターンとして、復興支援商品の購入もでき、お店の復興支援活動の場合は直接的なサポートができます。
クラウドファンディングで復興支援をするデメリットは、プロジェクトが必ずしも成功するとは限らないことです。ただし、復興支援プロジェクトの場合、多くが「All-In形式」を採用しており、目標金額に達しなかった場合は、集まった資金の範囲内で支援がおこなわれます。
万が一、プロジェクトが失敗したとしても、支援金は復興支援のために有効活用されるため安心です。








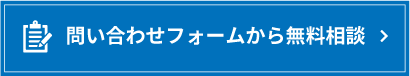
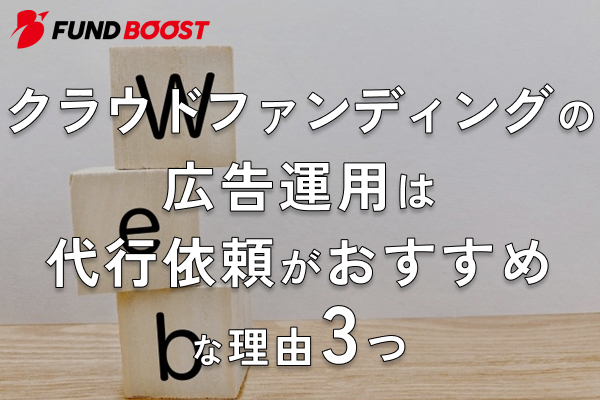
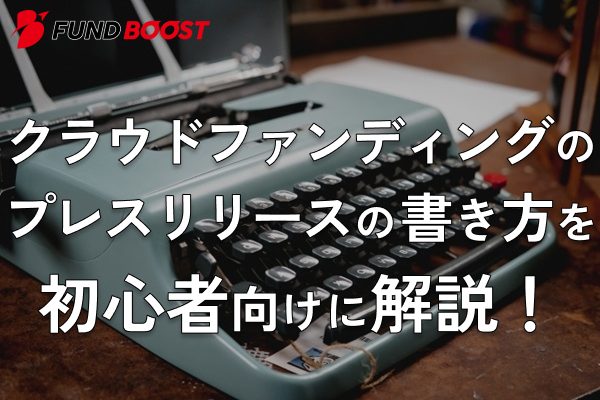


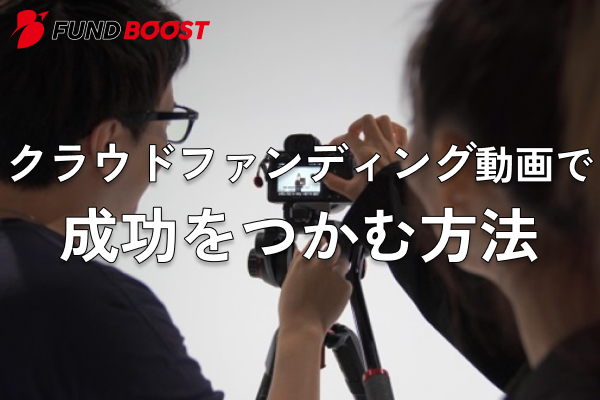
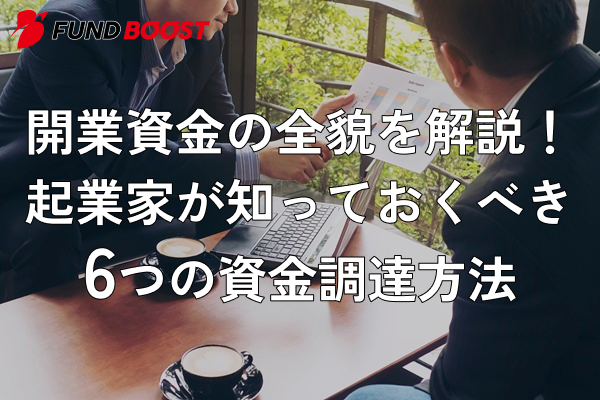


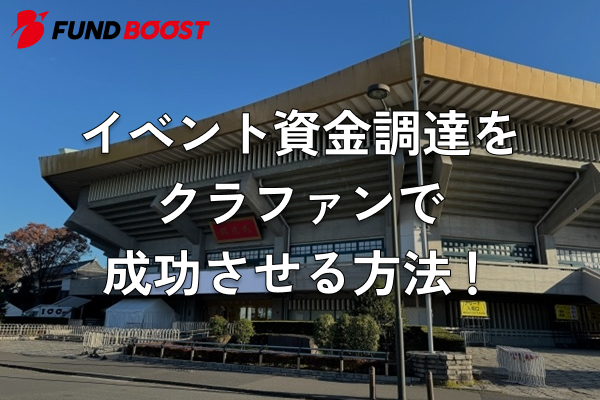
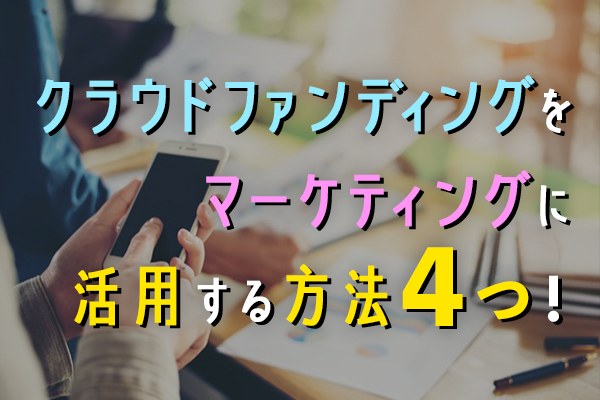
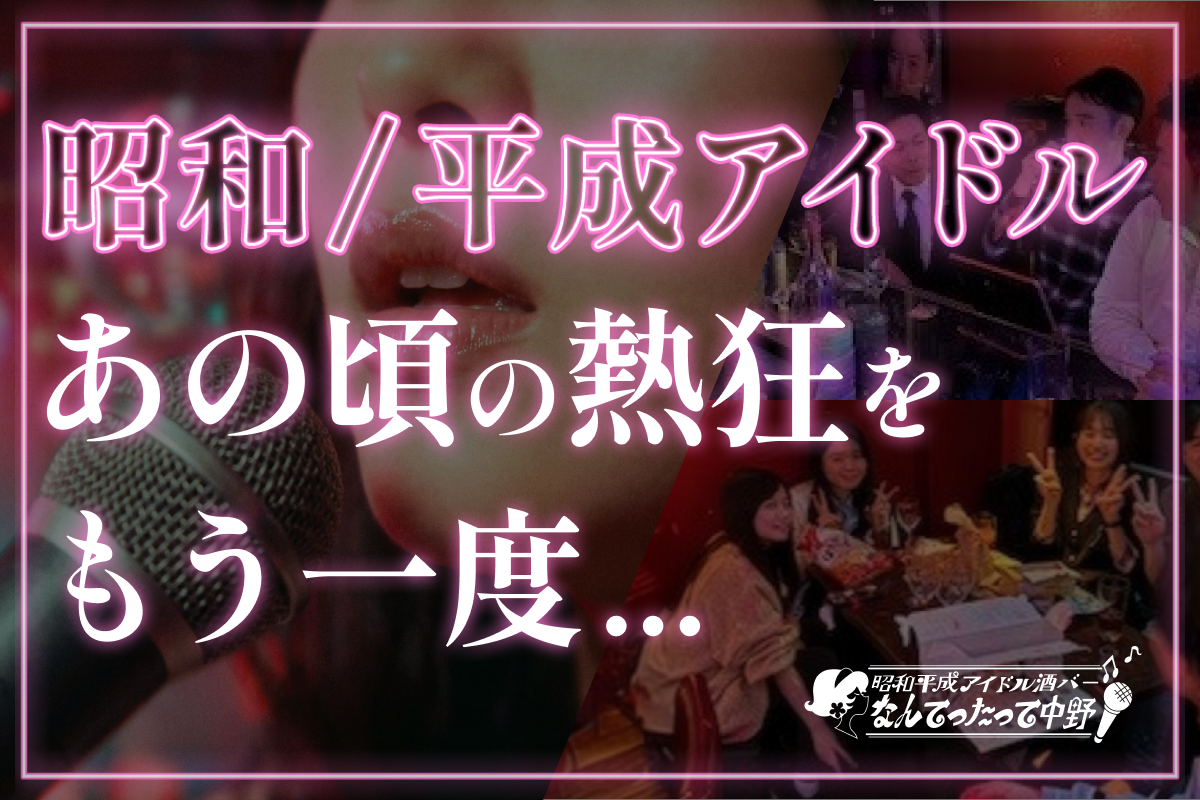
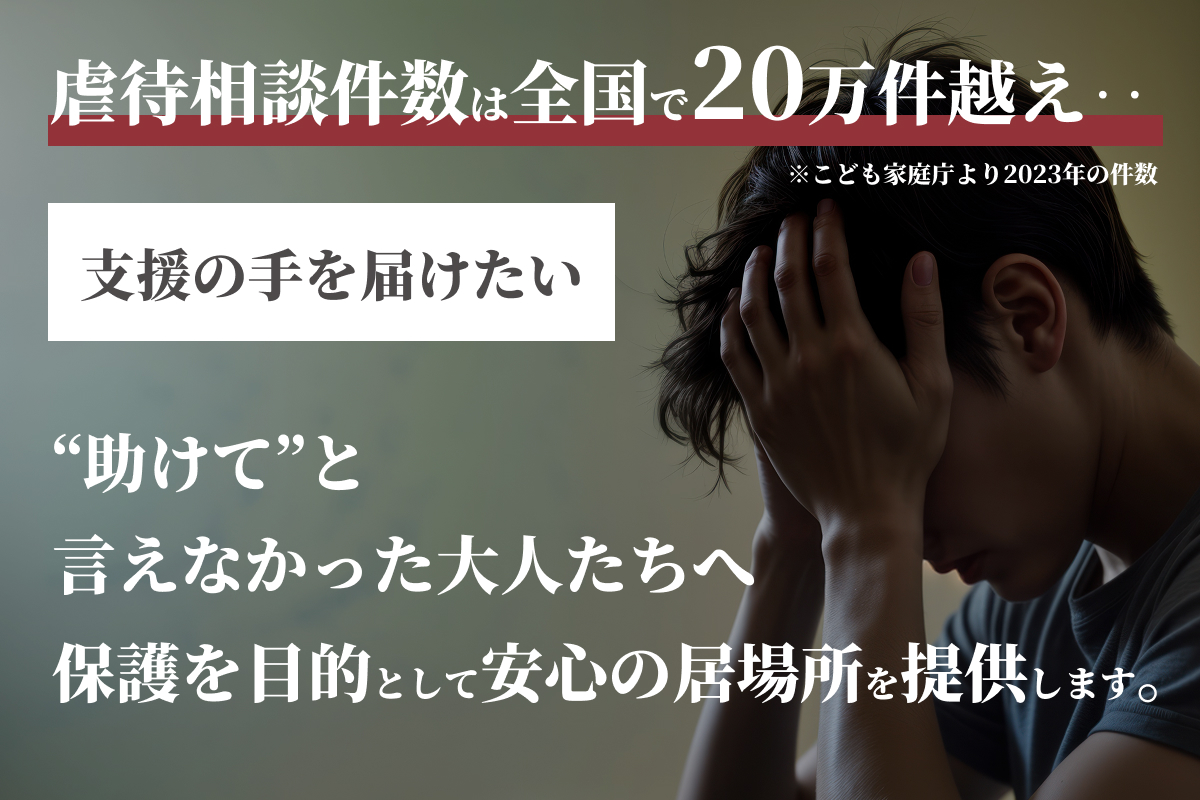
 LINEでお問い合わせ
LINEでお問い合わせ
クラウドファンディングのプロジェクトを成功に導くサポートをしております!